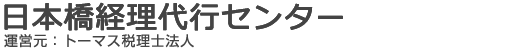スタッフブログ
確定申告はプロの税理士に頼みなさい!
中央区で創業支援をしている税理士の今井信吾です。
今回のブログでは、確定申告はプロの税理士に頼みなさ
いということについて
ご説明したいと思います。
最近、多いご相談は、仮想通貨の売買をされている方か
らのご相談です。
仮想通貨で年間数千万円の利益を上げています。
このまま確定申告をすると、1000万円程の納税となります。
この方には、以下のような節税対策を提案してみました。
税金の知識が乏しいと無駄な税金を払う可能性があります。
また、間違った節税は無駄で終わることがあります。
税務調査で確定申告の内容を否認されて受けるペナルテ
ィも高利貸しの比ではありません。
税務調査も間違いだらけ。
こんなことを言うと当局に叱られるかもしれませんが、
証拠がたくさんあります。
正しい知識がないと払う必要のない税金も払う羽目に。
「調査官にお土産持たせれば、すぐに帰るよ」なんて話
しを一部の税理士がしてるようですが、そんなことはあ
りません。まさに都市伝説。
間違ってないことまで認める必要はないのです。
経験上、経営者が納得しない否認案件は、税務署側が間
違っているケースが非常に多いのです。
合理的な節税と正しい税務調査は、資金繰りを良くし、
黒字経営をするためのポイントでもあります。
知らないと無駄の所得税を余計に収めてしまうことにな
ります。
このブログを読めば、所得税を節税でき、
そして税務調査の正しい対応もできるようになります。
そもそも確定申告とは、
日本の租税に関する申告手続を言い、個人が、その年1月
1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収
入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を
計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額
を確定することです。
仮想通貨の売買益がある場合も、原則、確定申告が必要
になります。
また、節税とは、税金を抑えて、手元のお金を増やすこ
とです。
節税には、タイムリミットがあり、12月末までにやらな
ければなりません。
そのためには、事前に今年の収支状況を試算する必要が
あります。
では、具体的な節税方法の説明をします。
1.先ずは青色申告にすることです。
青色申告承認申請書を青色申告を受けたい年の3月15日又
は開業の日から2ヶ月以内に税務署に提出しなければなり
ません。
さらに、一定水準の帳簿を作成が義務となります。
2.青色事業専従者給与を活用する(青色申告が要件)
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとお
りです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する
人をいいます。
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であ
ること。
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業
に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所
轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする
年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始し
た場合や新たに専従者がいることとなった場合には、そ
の開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以
内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、
給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、
届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与
に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長
に提出していること。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかも
その記載されている金額の範囲内で支払われたものであ
ること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当で
あると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
3.事業専従者給与を活用する(白色申告の場合)
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低
い金額です。
(1)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
(2)この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に
1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、
次のとおりです。
(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいま
す。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で
あること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の
営む事業に専ら従事していること。
(2)確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要
な事項を記載すること。
4.貸倒引当金を計上する
5.純損失の繰越控除を活用する
純損失の繰越控除を受けるためには、以下の要件を満た
していることが必要です。
(1)損失(赤字)が発生した年度において、期限内に青色
申告していること
(2)損失が発生した年度の翌年以降、連続して申告してい
ること
(3)青色申告であること
6.中古車両を活用する
4年落ちの中古車の場合、12ヶ月で経費化できます。1月
にAudiを700万円で購入すれば700万円が経費化できます。
付随費用も本体と区分すれば必要経費になります。
7.少額物品を購入する
(1)使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円
未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用
に供した年分の必要経費とします。
(2)取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産につ
いては、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は
特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得
価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に
供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入する
ことができます。
(3)一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日か
ら平成32年(2020年)3月31日までに取得した取得価額1
0万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用
を受けるものを除きます。)については、一定の要件の
下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの
取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経
費に算入できるという特例があります。
8.減価償却は定率法が節税効果が高い
この場合、「減価償却資産の償却方法の届出」の手続き
をして減価償却の方法を「定額法」から「定率法」に変
更しなければなりません。
9.特別償却や税額控除を適用する
機械を購入したり、研究開発などをした場合、その支出
した金額の一定額を特別償却費や税額控除できるもので
す。たくさん、ありますので、詳細は割愛します。
10.自宅の費用の一部を経費化する
自宅の一部を事務所や商品の荷物置き場などにしている
場合、面積比率などの合理的な方法で、家賃や水道光熱
費などを一部経費化できます。
11.開業前に所有している車両を事業用に一部利用す
ることで、減価償却費として経費化する
この場合、事業分と家事分とに按分しなければなりません。
12.小規模企業共済に加入する
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度
は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのため
の、積み立てによる退職金制度です。
現在、全国で約133万人*の方が加入されています。
掛金は全額を所得控除できるので、
高い節税効果があります。
将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリット
を受けられる、今日からおトクな制度です。
小規模企業共済のおトクな3つのポイント
ポイント1
①掛金は加入後も増減可能、
②全額が所得控除
③月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に
設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除でき
るため、高い節税効果があります。
ポイント2
①共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
②共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。
満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」
「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取り
の場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年
金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
ポイント3
①低金利の貸付制度を利用できる
②契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を
ご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。
13.中小企業倒産防止共済に加入する
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経
営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)ま
で借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる
税制優遇も受けられます。
経営セーフティ共済の安心の4つのポイント
ポイント1
無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等
の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」
の、いずれか少ないほうの金額となります。
ポイント2
取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難にな
ったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、す
ぐに借り入れることができます。
ポイント3
掛金の税制優遇で高い節税効果
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額
できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、
または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、
節税効果があります。
ポイント4
解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めてい
れば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、
掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
14.在庫の見直し
在庫は経費になりません。そこで、不良在庫などの処分
や価格の見直しで期末在庫を減らすことができれば、そ
の分、経費が増える仕組みとなっています。
評価損が計上できる要件は、以下の通り。
9-1-4 令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる
著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化し
たこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がな
いにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値
が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められ
る状態にあることをいうのであるから、
例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれ
に該当する。(昭55年直法2-8「三十一」、平17年課法
2-14「九」により改正)
(1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通
常の価額では販売することができないことが既往の実績
その他の事情に照らして明らかであること。
(2)当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、
型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売された
ことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売
することができないようになったこと。
15.不良債権は貸倒処理をする
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合
には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
(1)金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、
その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
①会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する
法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた
金額
②法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協
議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協
議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
③債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭
債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者
に対して、書面で明らかにした債務免除額
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収でき
ないことが明らかになった場合は、その明らかになった
事業年度において貸倒れとして損金経理することができ
ます。
ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後で
なければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの
対象とすることはできません。
(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対す
る売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その
売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとし
て損金経理をすることができます。
①継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力
等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合
において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのう
ち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除き
ます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務
者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はあ
りません。
②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用
より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
(法基通9-6-1~3)
16.貸倒引当金を計上する
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業
の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによ
る損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の
合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れた
ときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事
由による損失の見込額については、それぞれの事由に応
じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることが
できますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金
額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額
の合計額から除かれます。
17.未払費用を計上する
12月末で発生している費用で、支払いが翌年以降のもの
でも、発生した年経費になります。
例えば、15日締めの給与の場合、12月16日〜12月31日に
対応する給与は経費となります。12月末までにクレジッ
トカードで購入した消耗品などの費用も経費になります。
18.買掛金を計上する
上記17と同じようなことですが、仕入も12月末納品分ま
で計上できます。
例えば、末締めの翌々月10日支払いの場合、12月末締め、
2月10日払い分は仕入に計上できます。
19.短期前払費用を活用する
(1)前払費用
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務
の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年
度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応
するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、
役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
(2)短期前払費用
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を継続してその支払った
日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、
(1)にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入するこ
とが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合の
その借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応
させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期
前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入するこ
とは認められませんので注意してください。
(法基通2-2-14)
20.家族の医療費をまとめて医療費控除を使う
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と
生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を
支払った場合において、その支払った医療費が一定額を
超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額
(下記3参照)の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
21.住宅ローン控除の工夫
夫婦でローンを組めば一人で組むよりも多くローン控除
を受けれる可能性があります。収入が多い方に借入を多
くした方が有利です。
22.耐震工事やバリアフリー、省エネ改修工事をした
場合、支出額の10%くらいを税額控除できます。
23.法人化のタイミング
個人の所得が一定の額に行くと法人化した方が節税効果
が高くなります。税率の分岐点としては500万円くらいが
目安と言われています。
24.法人成りのメリット、デメリット
法人成りのメリットは、主に以下のとおりです。
(1)所得を分散できる
社長や家族への給与で所得を分散して、節税ができる。
(2)退職金が費用になる
事業主に対する退職金も原則として法人の費用となりま
す。 これによって節税することができます。
(3)生命保険料の一部又は全部が費用になる
事業主を被保険者とする生命保険に加入することにより、
その保険料の一部又は全部が法人の費用となります。
(4)社宅が費用になる
法人名義で事業主の自宅を借りることにより、社宅とし
てその家賃を法人の費用とすることができます。
(5)税率が一定(比例税率)である
法人税は原則として一定(中小法人の場合には軽減税率
あり)である「比例税率」となります。
・中小法人の軽減税率 … 所得のうち年800万円以下の
部分に対しては15%
800万円を超える部分に対しては、原則通り23.9%
(6)出張手当が使える
役員が国内、国外へ出張した場合、日当や支度金が支給
できます。所得税も非課税なので、なるべく活用をお勧
めします。この場合、旅費規程を定めることが必要です。
(7)赤字を10年間繰越して、控除できる
法人成りのデメリットは、主に以下のとおりです。
(1)社会保険の加入義務がある
従業員を雇っていなくても、報酬を受けている役員が1人
でもいれば、その法人は強制適用事業所に該当します。
(2)お金を自由に使えない
例え事業主であっても、法人のお金を私的なものに使う
ことはできません。
(3)赤字でも納付する税金(均等割)の負担がある
赤字であっても課される税金(住民税の均等割)があり
ます。
(4)手間が増える
確定申告の提出書類が煩雑になります。申告以外でも、
役員の任期満了に伴い登記が必要であったり、手間と共
に費用も増えることになります。
最後に個人事業主に行われた税務調査をご紹介します。
調査対象者はIT事業
調査官の指摘事項は、交際費を使い過ぎる
1日5〜6件の飲食店の領収書が毎日のようにある
こんな指摘はしょっちゅうありますが、
交際費が多いと経費とならないという法律は無いのです。
この方は営業として飲み会に参加しているので、問題な
いのです。
調査官に指摘されたら、法律的根拠を確認することが正
しい税務調査の対応の基本になります。
税務調査で怖気づいてしまい、調査官の言いなりになる
税理士が多いので、こんな間違ったことがまかり通って
しまうのでしょう。
まずは、経験豊富な税理士、会計事務所に相談されるの
が近道です。
本日は、確定申告はプロの税理士に任せなさい!
についてお伝えしました。
日本橋経理代行センターは、中央区を中心に
経理、記帳に関するサービスを提供しています。
開業間もない(開業予定)オーナーさんは、
お気軽にご相談下さい。